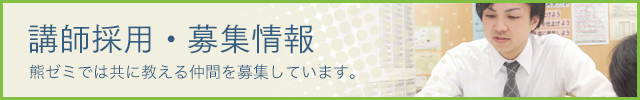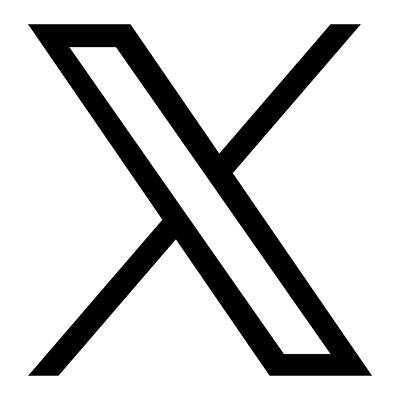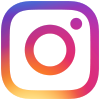【熊ゼミNEWS】どうなってる?高校入試の現状④
熊本の高校入試の現状④
熊ゼミNEWSでは,これまで3回に渡って,公立高校,私立高校,国立高専の現状と入試制度についてお伝えしてきました。今回は,近年進学する生徒が増えてきている『通信制』高校の現状についてお伝えしたいと思います。
◆不登校の現状◆
先日,文部科学省より2024年度の不登校調査が公表され,小中学校で年間30日以上欠席した長期欠席者,いわゆる不登校の児童生徒数は,全国で35万3970人と,12年連続で過去最多を更新しました。内訳は,小学生が13万7704人(前年度比5.6%増),中学生が21万6266人(前年度比0.1%増)で,小学生では44人に1人,中学生では15人に1人の割合で,40人学級の中学校の場合,1クラスに2人以上いる計算になります。
これを熊本県で見てみると,小中学校年間30日以上欠席した不登校の児童生徒数は5781人で,過去最多だった前年度より67人減少し,12年ぶりの減少となりました。内訳は,小学生が2133人(前年度比64人減),中学生が3648人(前年度比3人減)で,小学生では全国平均とほぼ変わらない44人に1人,中学生では全国平均よりやや多い13人に1人の割合となります。スクールワーカーの方や学校の先生方が協力することで,前年度より不登校の児童生徒数が減少したとはいえ,10年前と比較すると約3倍に増えていて,今後もそうした児童生徒にたいするさらなる支援が必要だと考えられます。一方,熊本県内の高校生の不登校者数は751人で,前年度より120人減少しました。不登校者数が小中学生に比べて少ないと感じた方も多いと思います。これは,義務教育である小中学校と違い,高校生の場合,出席日数が足りなければ進級できない,卒業できないという厳しい現実があるからです。途中で転校したり,中途退学する生徒も少なくありません。
◆通信制高校とは◆
通信制高校について説明する前に,まず全日制の高校との違いについてお話しておきます。
全日制の高校で,卒業資格を得るために必要なことは何でしょう? まず,みなさんの頭に思い浮かんだのは「出席日数」,そして「成績評定(中学校でいえば通知表)」でしょう。これに1つ付け加えるとすると,「3年間通学すること」でしょうか。全日制の高校の場合,「3年間以上の在学」と「74単位以上の修得」が,卒業資格を得るための最低限の条件として法的に定められています。一般に,ある科目の授業を1年間受け,定期考査等の試験である一定の成績をクリアすることで「1単位」が認められます。多くの全日制の高校では『学年制』をとっていて,学年ごとに修得すべき単位数(例:高校1年生で27単位,高校2年生で27単位,高校3年生で20単位など)を定めていて,これを満たした生徒が次の学年に進級できることになります。
この学年ごとの縛りをなくし,卒業までに必要な単位を修得すればよい『単位制』をとっている高校(湧心館高校や翔陽高校など)もあります。たとえば,翔陽高校の場合,国語や数学,体育など,共通の普通教科の科目に加え,「農業」「工業」「商業」「家庭」の4つの専門教科(系列)から,自分が興味がある教科(系列)を中心に科目を選択し,授業を受けることができます。これに「普通」を加えた5つの教科(系列)があり,「農業」「工業」の系列はさらに「園芸・造園」「食品製造」と「機械」「電気電子」「建築」の5分野に分かれていて,生徒たちは,学年が上がるごとに,自分が興味がある専門教科(系列)の科目を選択し,単位を修得できる仕組みになっています。こうした「総合学科」については,他の県立高校や私立高校でも採り入れているところがあります。
『通信制』高校とは,「3年間以上の在籍で,74単位以上を修得する」という『単位制』をとりながらも,毎日登校して授業に出席する義務がない高校になります。と言っても,学習指導要領で定められている高校で学ぶ内容をきちんと学習し,理解できているかどうかの確認は必要ですから,卒業資格を得るための条件として,以下のようなものが定められていいます。
◎通信制高校で卒業資格を得るための条件
①必履修科目を含む74単位以上の単位修得
②36か月以上の在籍期間
➂30単位時間以上の特別活動への参加
①の必履修科目とは,「数学Ⅰ」や「現代国語」,「情報」といった,高校卒業資格を得るために,すべての高校において履修が義務付けられている科目です。また,➂の特別活動とは,入学式や卒業式,文化祭のような学校行事と考えていただくとわかりやすいと思います。
【通信制高校における単位修得の仕組み】
毎日登校しなくてもよい『通信制』高校での学習は,「自学」が基本となります。全日制高校と同様に,学校が指定した教科書を生徒自身が学習します(※教科書によっては,動画による解説などの学習ガイドがついているものもあります)。予定していた単元の学習が終わると,生徒は教科書や学習ガイドにそった課題=レポートを提出します。一般的な学校の試験とは異なり,基本的な内容が中心で,教科書や資料を見ながら作成しても構いません。提出したレポートに,間違っているところや理解が不十分なところがあった場合,丁寧なコメントが記入され,再提出を求められる場合もありますが,高校では,このやり取りを通じて,学習内容を理解できているかどうかを知ることができます。この自学による学習とレポートの提出が,『通信制』高校に在籍する生徒にとっての普段の学習になりますが,年に数回実施される「スクーリング」に参加する必要があります。これは,わかりやすく言うと「対面の授業」です。これには,教室で行う授業だけでなく,体育のような実技科目も含まれます。そして,最終的に「単位認定試験」に合格することで,その科目の単位修得が認められます。全日制の高校の定期考査にあたるものですが,教科書の基礎・基本的な内容が中心ですので,難易度的にはそこまで難しいものではありません。
◎単位修得の流れ
①教科書等を使った自学
②レポートの提出
➂スクーリングへの参加
④単位認定試験の合格
【通信制高校に通うメリット】
『通信制』高校の最大の特徴は,毎日登校しなくてもよいことです。なかなか学校に通えない,あるいは,学校には行っても教室の中に居づらさを感じるという人にとっては,自宅で,自分のペースで気負わずに勉強できるというメリットがあるでしょう。また,クラブチームに在籍していて,将来はプロのアスリートをめざしているという人にとっては,昼間の時間をクラブチームでの練習や自分のトレーニングに集中し,夜の時間を自分の勉強にあてることができるというメリットがあります。ただし,これは逆に言うと,しっかりと時間の使い方を考えなければ,楽な方に流されてしまいかねないということにもなります。年に数回(修得したい単位数にもよりますが,だいたい10日~15日程度)行われる「スクーリング(対面授業)」と「単位認定試験」,3年間で30単位時間の「特別活動(学校行事)」以外の時間をどう使うか。保護者の方の中には,そこを不安に感じる方も少なくないと思います。
こうした,昼間の自由に使える時間を有効に使えるように,『通信制』高校に通う生徒を支援する施設が2種類あります。1つは『面接指導等実施施設』で,一般的には「学習センター」,あるいは「〇〇キャンパス」と呼ばれるものです。これは,都道府県や文部科学省の認可を受けた学校施設の一部で,その名の通り,本校同様に「スクーリング」や「単位認定試験」を実施できる施設で,スクールカウンセラーを常設し,生徒たちの生活面や心理面でのケアにあたっているところもあります。もう1つは,『学習等支援施設』で,一般には「サポート校」と呼ばれます。こちらは,正確には学校施設ではない民間の教育施設で,『通信制』高校と提携し,主に学習面を中心とした支援を行っています。『通信制』高校に通う生徒専用の「塾」といった方がわかりやすいでしょうか。自学ではなかなか難しい大学受験に向けた授業や,資格・検定取得のための講座などを開講していて,対面授業だけでなく,オンラインの講座を用意しているところもあります。ただし,「サポート校」はあくまでも『通信制』高校に通う生徒たちの塾的な存在ですので,ここでの勉強だけでは卒業資格を得ることはできません。「サポート校」を活用することで,『通信制』高校であっても,全日制高校に近い,大学受験や専門学校進学に向けた勉強を,より質の高いものにすることが可能になります。
本来,学校施設である「学習センター」と,民間施設である「サポート校」は別個のものですが,同じ敷地内に併設されている場合もあります。その場合,普段は「サポート校」の施設で勉強し,「スクーリング」時や「単位認定試験」の際は,同じ敷地内にある「学習センター」で受けるといったことも可能になります(※「サポート校」のみの場合,「スクーリング」や「単位認定試験」は本校,または「学習センター」まで行って受ける必要があります)。
また,ニュース等で私立高校に対する就学支援金の拡充と所得制限の撤廃,いわゆる「私立高校の授業料無償化」について耳にされている方も多いと思います。こちらの記事をアップした2025年11月15日の時点では,まだ正式決定はされていません。しかし,過去の熊ゼミNEWSでも触れた通り,全日制私立高校の授業料無償化については,2026年度からの導入に向けて動き始めています。これは『通信制』高校においても同様ですが,年間の授業数,単位数がはっきりしている全日制(学年制)の高校とは仕組みが異なるため,詳しくは制度が確定しないとわからない部分もあります。このため,2027年度からの導入になる可能性もあります。実際に所得制限が撤廃された場合には,現在,世帯年収590万円未満の家庭に対してのみ支給されている就学支援金,年間最大33万7000円が,全生徒に適用されることになります。
◆くまもと清陵高校の誕生◆
2005年,熊本ゼミナールが九州初の株式会社立高校として,熊本県南阿蘇に立ち上げた『くまもと清陵高等学校』は,単位制・広域通信制の高校になります。「広域通信制」とは,本校がある都道府県だけでなく,他の都道府県にも「学習センター」などの学校施設をもつ『通信制』高校を表します。2017年に学校法人となり,今年,創立20周年を迎えました。「学習塾である熊ゼミが,なぜ通信制高校を?」と思われる方も多いかもしれません。
ここで,ちょっと『くまもと清陵高校』誕生の歴史について触れておきます。『くまもと清陵高校』創立20周年となる今年,熊ゼミも創立40周年を迎えました。熊ゼミの歴史の半分は『くまもと清陵高校』と共にあるわけです。『熊本ゼミナール』が誕生した1985年は,バブル景気〔バブル経済〕が本格的になり始めたころで,小中学生対象の学習塾として誕生した熊ゼミも,やがて熊本市内外に校舎を展開し,大学受験をめざす高校部も持つ総合学習塾へと成長していきました。当時は,高学歴を求める,いわゆる受験戦争が最も過熱していた時代で,学校の休みが続くことは「登校拒否」と呼ばれていました。「登校拒否」する子ども自身の精神状態や家庭内に原因があり,一般的には「個人の問題」であるかのようにとらえられていたのです。バブル景気が続く中で,この「登校拒否」児童の数は次第に増え,社会的にも認知されるようになります。1990年代になると,子ども自身や家庭内だけでなく,学校内(いじめ,先生や友だちとの関係,学校生活に適応できないなど)に原因がある場合もあるという認識が徐々に広まり,文部科学省も,「登校拒否」ではなく「不登校」という用語を使うようになります。学校の長期欠席が続くことを,様々な背景で,学校に行きたくても行けない状況ととらえられるように変わってきたのです。熊ゼミに通う生徒たちの中にも,いわゆる「不登校」の悩みを抱える生徒たちは増えていきました。普段,学校になかなか通うことができない生徒たちの中にも,学校と環境が違う塾なら通うことができるという生徒はいます。学校を休んで習っていないところがあるため,塾で一生懸命勉強してくれる生徒も少なくありません。当然,こちらも一生懸命教えます。そうやって苦労して,何とか目標としていた高校に合格。しかし,高校に入学後に「不登校」となり,結果として高校を辞めてしまう生徒もいるのです。熊ゼミが,その誕生から大切にしてきた言葉に『めんどう見』があります。努力して高校に送り出した生徒が辞めてしまう状況に対し,このままでいいのか,この状況を変えるために,熊ゼミに何かできることはないのか。そう模索し続ける中,2001年に内閣総理大臣となった小泉純一郎首相が示したのが「構造改革特区制度」でした。特定の地域や分野を限定して国の規制を緩和し,その地域の活性化や経済社会の構造改革を推進する制度です。ちょっと難しいですね。わかりやすく言うと,「その地域(都道府県や市町村)が元気になったり,潤ったりする取り組みであれば,国の規制を緩めて応援しますよ」という制度です。これを活用し,2005年に熊本県南阿蘇村に誕生したのが『くまもと清陵高等学校』です。「実学」「環境」「農育」をキーワードに,教科学習はもちろんのこと,農業体験,職業体験,企業インターンシップなどの体験型の「特別活動」を多く取り入れ,「自分のやりたいこと」「将来,自分がなりたいもの」を発見する『自己実現』を実践する新しいコンセプトの単位制・広域通信制高校をめざしてスタートしました。2017年には『学校法人 熊ゼミ学園 くまもと清陵高等学校』として新たに生まれ変わり,熊本市内に『熊本学習センター』を開設,公認心理士の資格をもつスクールカウンセラー2名体制で,「学力」と「こころ」の両面からサポートする体制を整えています。
◆くまもと清陵高校の今◆
冒頭でも述べましたが,2020年からのコロナ禍を経て,「不登校」の児童生徒数は一気に増え,国や都道府県,市町村の取り組みも変化してきました。『通信制』高校を進学先に選ぶ生徒も増え,『通信制』高校に対する社会の見方も変わってきました。
「スクーリング」や「単位認定試験」を実施する南阿蘇にある本校と,普段の学習面,生活面でのサポートをする熊本市内にある付属施設「学習センター」。そして,「学習センター」と同じ敷地にあり,主に「学力」面でのサポートを中心とする熊本ゼミナールの「教育センター」。熊本から始まった『くまもと清陵高校』の歴史は,今や県外にも広がっています。2025年現在,滋賀県大津市に「滋賀学習センター」,福岡県福岡市に「福岡学習センター」,東京都新宿区に「東京学習センター」を開設し,それぞれ「東近畿高等学院」「学思館高等学院」「ベネッセ高等学院」によるサポートが行われています。これまで,本校がある熊本ではできるだけ「対面」での指導にこだわった「めんどう見」を重視してきました。社会で生きていくためには,「人」との関わりが不可欠であり,「人を育てるのは人」という考えからです。しかし,3年余り続いたコロナ禍で,オンラインを使った学習も急速に進化しました。大学受験や資格検定取得に向けた,充実したオンライン講座をもつ「ベネッセ高等学院」との提携で,全国,どこに住んでいても,オンラインでのサポートを受けることができるようになりました(もちろん,「スクーリング」や「単位認定試験」,「特別活動」は,本校または最寄りの「学習センター」で受ける必要はありますが)。
『くまもと清陵高校』のホームページや学校案内には「#みらいにつながる きみのゆめ」との表記があります。また,ちょっと難しい言葉ですが「未来邂逅」と「自分発見」という言葉があります。一度見失った夢でも,『くまもと清陵高校』で過ごす時間の中で,自分の居場所を見つけ,自分のやりたかったこと,なりたかった自分をもう一度発見してほしいという願いから生まれた言葉です。「邂逅(かいこう)」とは,思いがけず巡り合うことや偶然の出会いを意味する言葉ですが,奇跡的なめぐり逢いを表す場合に使われることもあります。『通信制』高校を選択する。このことだけでも,生徒本人にとっては勇気のいる選択かもしれません。でも,そこで一歩踏み出すことで,将来の奇跡的な出会いにつながる可能性も高まります。
『通信制』高校の説明をするはずが,半分『くまもと清陵高校』の話になってしまいましたが,もし興味を持たれたり,不登校で悩まれたりしている方がいらっしゃるなら,まずは相談をされてみてください。入試日が決まっている全日制の高校とは異なり,入学(転入学・編入学を含む)の時期は決まっていませんし,学力試験もありません。焦らずともよいので,じっくりと話を聞いてみてください。決めるのはそれからでも遅くありません。
※次回の熊ゼミNEWSは,「共通テスト結果速報」として,10月に実施された共通テストの結果分析と主な高校の合格ライン予想についてお伝えしたいと思います。